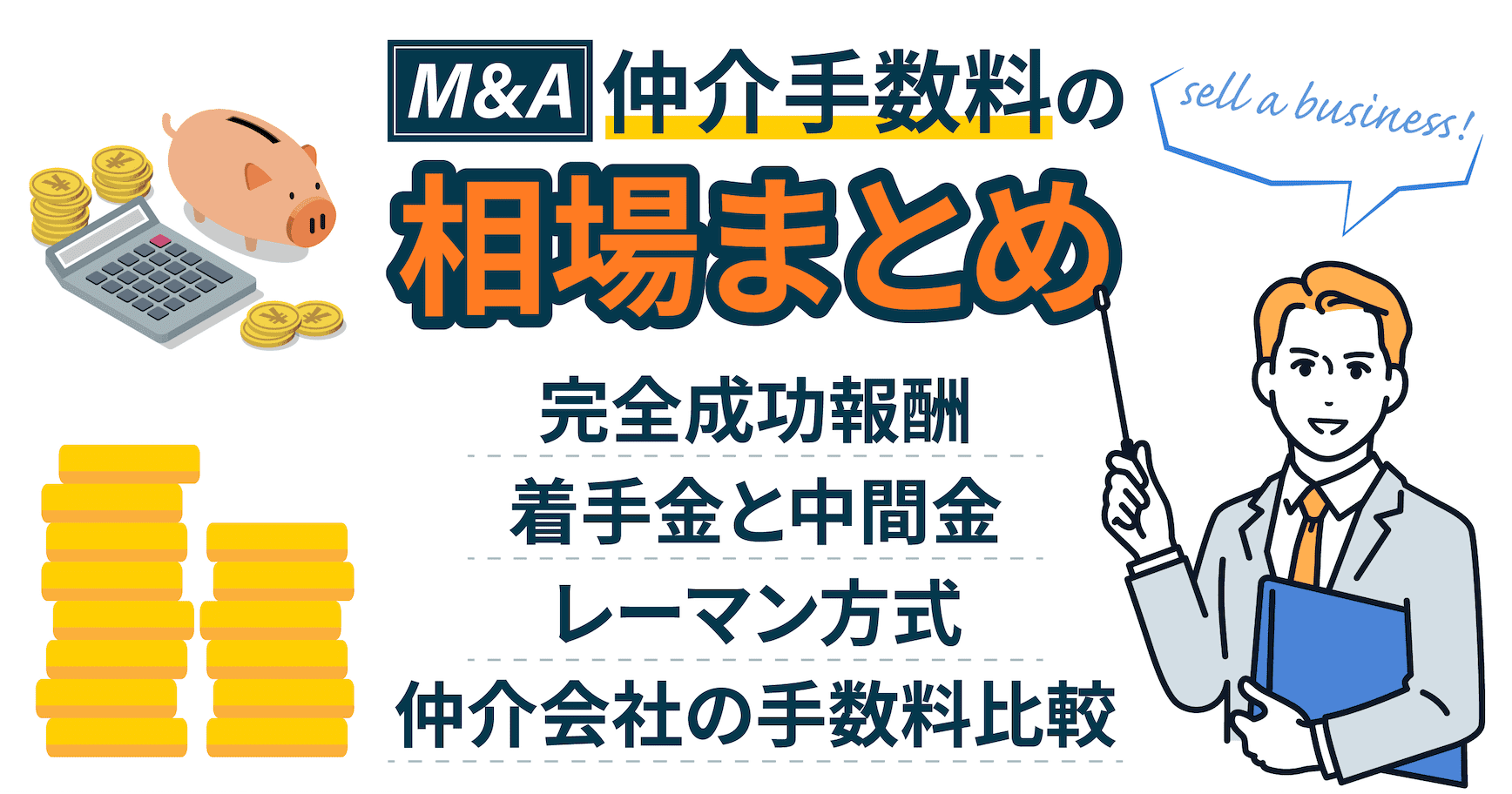M&A仲介会社を選ぶ上で一番重要なポイントは、手数料です。一口に手数料と言っても、着手金、月額報酬、中間金、レーマン方式による成功報酬などの手数料があります。
 MAアドバイザー
MAアドバイザー仲介会社ごとに必要な手数料は大きく異なり、安いところと高いところを比較すると数百万円から数千万円も手数料に差が出るケースがあります。
M&Aの手数料は売り手と買い手の双方がM&A仲介会社に支払います。
手数料の支払いタイミングは大きく2つあります。M&Aが成立した場合にだけ手数料を支払う仲介会社(完全成功報酬型)と、M&Aの成否に関わらず手続きの段階ごとに手数料の支払いが必要な仲介会社があります。
ここではM&A仲介手数料の相場と注意点を徹底解説して、主要な仲介会社の手数料を比較します。
M&Aの手数料は誰が払う?
M&Aの手数料は誰が払うかは、売り手側と買い手側それぞれが仲介会社に支払います。金額は売り手と買い手共に同額が一般的です。
株式譲渡と事業譲渡によって、誰が仲介会社に手数料を払うかが変わります。
| 株式譲渡 | 売り手:株主(主に社長個人)が仲介会社に手数料を支払う 買い手:買い手の会社が仲介会社に手数料を払う |
| 事業譲渡 | 売り手:売り手の会社が仲介会社に手数料を支払う 買い手:買い手の会社が仲介会社に手数料を支払う |
売り手と買い手の手数料の違い
M&A仲介会社に依頼する場合、原則手数料は売り手と買い手も同額ですが、一部の仲介会社は買い手に対して追加で手数料を請求する場合があります。
例えば売り手と買い手が面談をする場合、仲介会社は買い手に面談手数料を請求するケースがあり、M&A交渉上で不都合が生じる場合もあります。
M&A仲介の手数料の相場と内訳
M&A仲介会社に支払う手数料として一般的なものは着手金、月額報酬、中間金、成功報酬の4つです。いずれも小さな金額ではないため、どのようなものか順に説明します。
完全成功報酬型とそれ以外の違い
完全成功報酬型は、成功報酬のみ受け取るM&A仲介会社です。着手金、月額報酬、中間金がかからないので、M&Aが成立しなかった場合は、仲介会社にお金を支払う必要はありません。
着手金、月額報酬、中間金がある仲介会社は完全成功報酬型ではありません。M&Aが成立しなかった場合でも、数十万円から数百万円の手数料が発生します。
①着手金の相場
着手金とはM&A仲介会社に正式に依頼する際にかかる費用のことです。
M&Aは買い手探しを開始する前に様々な調査や資料作成業務が発生するため、そのための費用を最初に請求される場合があります。
最近では着手金がかからないM&A仲介会社も増えていますが、着手金を請求する仲介会社だと中小企業のM&Aでは着手金の相場は数十万円から100万円前後、大規模なM&Aでは数百万円ほどかかります。
着手金を払うメリットは、M&A仲介会社が丁寧な準備をしてくれる可能性が高まることです。企業価値算定や事前のデュー・デリジェンス、企業概要書などを工数をかけて実施/作成してもらえたりします。
着手金を払うデメリットは、一度支払うと戻ってこないことです。そして着手金を支払ったからといって必ずしも丁寧な準備をしてもらえるわけではないです。
M&A仲介会社や担当によって対応品質が変わるため、最初の相談や面談を通じて、着手金を支払う前に支払うに値する相手か見極めることが重要です。
着手金は株式譲渡だと会社の費用としては計上できず、社長個人のポケットマネーで支払う必要がある点も注意です。
②月額報酬(リテイナーフィー)の相場
月額報酬(リテイナーフィー)とは、M&A仲介会社と契約後に毎月支払う金額のことです。月額報酬は一度支払うと戻ってこないお金です。
月額報酬は担当するM&Aアドバイザーの資料作成や買い手候補先開拓、交渉などの業務活動に対して支払われる対価として請求される場合があります。
最近では月額報酬がかからない仲介会社が多いですが、月額報酬を要求する仲介会社だと担当するアドバイザーにもよりますが、相場としては月額数十万円前後です。
月額報酬は大規模会社の場合に存在することが多いですが、中小企業でも一部存在します。中小企業のM&A の場合、月額報酬を要求する仲介会社は避けた方が良いです。お金がもったいないです!
③中間金の相場と注意点
中間金とは売り手と買い手との間で基本合意が締結されたタイミングで支払う手数料のことです。
最近では中間金がかからない仲介会社も増えていますが、中間金を請求する仲介会社だと仲介金の相場は成功報酬の10~20%前後が多いです。
中間金をとる仲介会社の場合でも、仲介会社によって中間金の扱いが変わります。
| 基本合意後 | 中間金の扱い |
|---|---|
| M&A成約 | 通常の仲介会社:中間金を成功報酬から差し引く 一部の仲介会社:中間金を成功報酬から差し引かない |
| M&A不成約 | 通常の仲介会社:中間金を返金する 一部の仲介会社:中間金を返金しない |
中間金は無事に成約した場合、通常は成功報酬から中間金が差し引かれますが、一部の仲介会社は成功報酬から中間金を差し引かない会社もあります。
また基本合意後にM&Aが不成立になった場合、通常は中間金は返金されますが、そうでない仲介会社も多数存在しているので注意が必要です。
基本合意後にM&Aが不成立になる可能性は?
基本合意後にM&Aが不成立になる可能性は実は50%もあります(業界、規模、具体的な状況次第で変動)
基本合意後でもM&A不成立の可能性が高いため、中間金についてはシビアに情報収集を行った上で、M&A仲介会社を選ぶことが重要です。
④成功報酬の相場とレーマン方式の違い(譲渡金額/時価総資産/時価純資産)
成功報酬とはM&Aが成立した際に仲介会社に支払う手数料です。成功報酬は仲介会社に支払う手数料の中で最も大きな金額です。
ほとんどの仲介会社はレーマン方式で成功報酬を計算します。レーマン方式とは、計算基準数値によって手数料率が変動する計算テーブルを用いる算出方式です。
| 計算基準(譲渡金額 or 時価総資産 or 時価純資産) | レーマン方式の手数料率 |
|---|---|
| 100億円超 | 1% |
| 50億円超〜100億円以下 | 2% |
| 10億円超〜50億円以下 | 3% |
| 5億円超〜10億円以下 | 4% |
| 5億円以下 | 5% (例:5億円 x 5% = 成功報酬2,500万円) |
M&A仲介会社によってレーマン方式の計算基準が異なります。通常は譲渡金額が計算基準になりますが、一部の仲介会社は時価総資産や時価純資産を計算数値にしています。
この計算基準の違いで、成果報酬額が大きく異なる場合があります。
下記の資産構成の会社Aの株式譲渡(会社譲渡)を例に計算基準の違いを説明します。
| 資産10億円(時価10億円) | 負債5億円(時価5億円) 純資産5億円 (年間利益1億円x3年間=将来得られる価値3億円) |
譲渡金額を計算基準にしたレーマン方式の成功報酬
成功報酬の計算方法で最も一般的な方法は、譲渡金額を基準としたレーマン方式です。
簡単に譲渡金額を説明すると買い手から受け取る金額です。会社売却の場合、一般的に純資産の額と将来得られるであろう金額の合計額が譲渡金額になります。
会社Aの譲渡金額は、純資産5億円と将来得られる価値3億円の合計額で8億円です。譲渡金額で成功報酬を計算すると、成功報酬は3,700万円です。
計算式:2,500万円(5億円×5%)+1,200万円( 3億円×4%)=成功報酬3,700万円
時価総資産を計算基準にしたレーマン方式の成功報酬
成功報酬の計算方法で譲渡金額の次に一般的な方法は、時価総資産を基準としたレーマン方式です。(時価総資産を採用している大手のM&A仲介会社はM&Aセンターだけ)
時価総資産とは譲渡日の時点で会社が持っているすべての資産の時価のことです。土地や設備を保有している企業だと決算書上の簿価と時価で金額に差分が生まれるため注意が必要です。
会社Aの時価総資産は10億円です。時価純資産で成功報酬を計算すると、成功報酬は4,500万円です。
計算式:2,500万円(5億円×5%)+2,000万円( 5億円×4%)=成功報酬4,500万円
時価純資産を計算基準にしたレーマン方式の成功報酬
成功報酬の計算方法で少数派の方法は、時価純資産を基準としたレーマン方式です。(時価純資産を計算基準としているM&A仲介会社はオンデックくらいです)
純資産とは会社の資産から負債を差し引いたものとなり、それを時価に直したものが時価純資産です。
会社Aの時価純資産は5億円です。時価純資産で成功報酬を計算すると、5億円×5%で成功報酬は2,500万円です。
最低手数料(最低報酬)に要注意
成功報酬は一般的にレーマン方式と呼ばれる計算テーブルによって算出されますが、2,000万円~2,500万円の最低手数料を設定しているM&A仲介会社が一般的です。
成功報酬が2,500万円以下になりそうな場合は、M&A仲介会社ごとに設定されている最低手数料に注意が必要です。
例)最低手数料2,000万円のM&A仲介会社で譲渡金額2億円のM&Aが成立
レーマン方式で譲渡対価2億円の手数料率は5%なので、2億円 x 5%で1,000万円が成功報酬です。ただし、最低手数料は2,000万円なので、この場合は2,000万円の成功報酬を仲介会社に支払う必要があります。
仮に最低手数料が1,500万円の仲介会社だった場合は、上記の例だと成功報酬は1500万円になります。
成功報酬請求タイミングに要注意
成功報酬はM&A仲介会社に支払うタイミングにも注意が必要です。
最終合意が締結されてM&Aが成立した場合でも、何らかの事情で買い手から譲渡対価が支払われず、M&Aが不成立になる場合がごく稀にあります。
ほとんどのM&A仲介し会社は最終合意後でもM&Aが不成立になった場合は成功報酬を請求しませんが、ごく一部のM&A仲介会社は成功報酬を請求する場合があります。
M&A仲介会社が手数料などを正確に公開しない理由



ほとんどのM&A仲介会社は手数料などの詳細情報をネットで公開していません。実際のところは聞いてみないとわかりませんが、最も多い理由が「問合せが欲しいから」です。
多くの仲介会社は営業力に強みを持っているため、一度問合せを行ってもらうことは接点を持つという意味で彼らにとっては喉から手が出るほど欲しい行動となります。
その他の理由として考えられるのは、多くのM&A仲介会社が手数料率を公開していない中で、仮に自社のみ公開してしまうと、まずは手数料を公開していない他社に問合せをされてしまうリスクが高まります。
このような理由で仲介手数料の詳細を公開しない会社が多くなっています。
相談料はかかる?
初めての相談タイミングでは費用はかからないので、良いM&A仲介会社を選ぶために複数の仲介会社に相談することをおすすめします。
相談自体はそこまで気構える必要はありませんが、仲介契約をする際には注意が必要です。仲介契約で重要なのは、専任契約を要求するM&A仲介会社は避けること、それとあまり多くの仲介会社と仲介契約を結ばないことです。
仲介会社の中には半年~1年間は他の仲介会社への依頼は禁止する専任契約を要求してきますが、専任契約を結ぶメリットは売り手側には無いです。
仲介契約前の相談自体は複数社に相談するのがおすすめですが、多くの仲介会社と仲介契約を結ぶとデメリットの方が大きくなります。
- 複数社と仲介契約するデメリット①対応労力が増加しすぎる
-
多くの仲介会社と仲介契約を結んでしまうと、仲介会社の数だけ対応労力が増えてしまいます。
- 複数社と仲介契約するデメリット②情報漏洩リスクが上がる
-
仲介会社によって機密保持のレベルや基準が大きく異なり、中には売り手の指示や依頼に従わない会社や担当者は存在します。そのため信頼できる会社を数社選定し進行することが望ましいです。
- 複数社と仲介契約するデメリット③出回り案件として買い手が認識する
-
複数の仲介会社を利用することでよくある失敗が同じ買い手に複数の仲介会社から紹介をしてしまうことです。こうなると買い手側は出回り案件(売り急いでいる案件)という心象となってしまい、足元を見られてしまいます。自分でコントロールできる数の仲介会社に限定して進めることが望ましいです。
M&A仲介会社の手数料の詳細比較、手数料が高い/安い仲介会社
主要なM&A仲介会社の手数料の詳細は紹介します。自社の資産構成や収益性、仲介会社の計算基準などで手数料が数百万円以上変わってきたりします。不明な箇所は、詳細が分かり次第追加します。
| 仲介会社 | 着手金 | 中間金 | 成功報酬の基準(最低手数料) |
|---|---|---|---|
| 日本M&Aセンター | あり(詳細不明) | あり(詳細不明) | 時価総資産 (推定2,500万円) |
| M&Aキャピタルパートナーズ | なし | 成功報酬の10% | 譲渡金額 (推定2,500万円) |
| ストライク | なし | 100万円〜300万円 | 譲渡金額 (2,000万円) |
| M&A総合研究所 | なし | なし | 譲渡金額 (推定2,500万円) |
| オンデック | 30万円 | 成功報酬の10% | 時価純資産 (推定2,000万円) |
| 名南M&A | 不明 | 不明 | 不明 |
| ペアキャピタル | なし | 成功報酬の10% | 譲渡金額 (推定2,000万円) |
| インテグループ | なし | なし | 譲渡金額 (1,500万円) |
| fundbook | なし | なし | 譲渡金額 (2,500万円) |
| M&Aコンサルティング | なし | なし | 譲渡金額 (推定2,000万円) |
| M&Aベストパートナーズ | なし | 成功報酬の10% | 譲渡金額 (推定1,500万円) |
| パラダイムシフト | なし | なし | 譲渡金額 (500万円) |
| ウィルゲート | なし | なし | 譲渡金額 (200万円) |
| サイトストック | なし | なし | 成約金額の10% (10万円) |
M&Aの手数料が高い!手数料が安い仲介会社でも大丈夫?
M&A仲介会社を選ぶ場合、仲介手数料の大小も重要ですが、同じくらいに重量なのは支払う手数料に対して見合う価値があるかです。
自らの会社や事業を納得のいく条件で買ってくれる買い手をいかに連れてきてくれるか、そして最後の交渉完了までサポートをしてくれるかが重要です。
安かろう悪かろうだけでなく、M&A仲介会社によっては高かろう悪かろうといった会社も一定数存在します。しっかりと見極めた上でM&A仲介会社に依頼することが重要です。
- 自社とシナジーのある買い手が具体的に何社いるか、それはどこか、既に繋がっているか
- 自社と類似企業/事業の支援実績があるか
- 社内外に専門家はいるか、どういった関わり方なのか
仲介手数料を値切るメリットとデメリット
一部の仲介会社で仲介手数料の値切りに応じる場合がありますが、無闇に値切り交渉はしない方が良いです。
手数料の値下げ要求が激しい売り手会社だと、面倒な客だと見なされて、仲介会社は密かに対応の優先度を下げていたりします。
明確な理由がない中での値切り交渉は成功確立が低く、ただ関係性を悪くしてしまうリスクがあります。



実際に値切り交渉をする人は10人に1人ほどですが、成功するケースは並行して依頼を想定している他社と比較して高いなどの明確な理由がある場合に限られることが多いです。
M&A仲介会社よりもアドバイザリーに頼めば手数料が実質半額になる?
M&Aの専門会社には、大きく分けて仲介会社とFAと呼ばれるアドバイザリー会社が存在します。
仲介会社は手数料を売り手と買い手の両方からもらいますが、アドバイザリーは手数料を売り手または買い手の片側からしかもらいません。
ここで疑問になるのが下記のケースです。
仲介会社 買い手から5% 売り手から5% 合計10%の手数料を取る FA 買い手から0% 売り手から5% 合計で5%の手数料を取る 合計手数料が実質半額になるのだから、FAを利用した方が手取りが多くなるはず
買い手が手数料を払わなくてもいい分、買い手が譲渡金額を上乗せしてくれるかというと、実務的にはならないです。
理由はシンプルで、買い手の主目的は投資回収を確実かつ1日でも早くすることのためです。(つまり手数料がない、ラッキーで終わります)
買い手が譲渡金額を上乗せするケースは、競争環境にある時のみです。
FAは専門性が高いですが、繋がりは仲介会社と比較して少ない会社が多く(専門家集団なので営業が苦手&専門作業に必死で営業する時間がない)、単独でのディール進行(売り手FAが買い手を直接連れてくるケース)は構造上競争環境が作り出しにくいです。
作り出せるとしたら買い手FA(仲介会社が多いです)と組むことが基本必要となり、そうなると結局買い手側にも手数料がかかります。
またFAはそもそも期待手数料が半分のため、一定規模以上の案件(目安譲渡金額10億円以上など)しか対応してくれないというそもそもの話もあります。